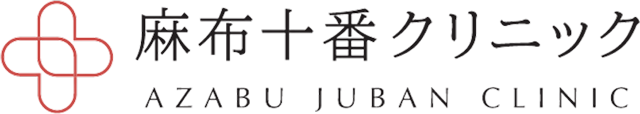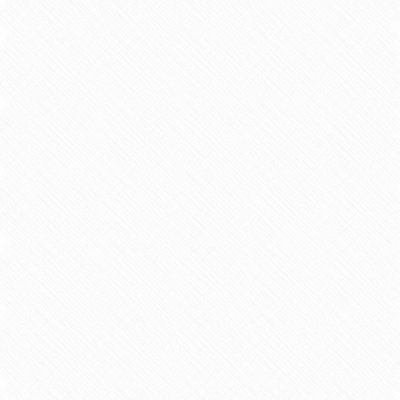最近、8月も終わりに近づいているのにまだまだ酷暑が続き、当院でも不眠のお悩みの方が大変増えています。これまでの導入剤をはじめとしたお薬では効かなくなってしまった、暑すぎてエアコンをつけっぱなしだと体が冷えてしまい、中途覚醒するようになった、というご相談をいただくことが多いです。適宜、お薬を調整することはもちろん大切ですが、その前に、よい睡眠のための5原則(睡眠衛生)をお伝えします。
1.睡眠原則① 「睡眠はもっとも重要な休養行動です」
理想とされる睡眠時間は、6~7時間ですが、本当に必要な睡眠は、実は個人差があります。高齢者は睡眠時間は短くなるのが自然ですが、絶対に8時間!という強迫観念を持ちすぎないでください。熟睡できた、休めた、と実感できればOKです。からだとこころの休養感が一番大切なポイントです。量(時間)と質(休養感)を見直しましょう。睡眠時間は短すぎても長すぎても健康を害する原因となります。朝起きたタイミングで、「ゆっくり休んでリフレッシュできた!」と思えることを目指します。
2.睡眠原則② 「光、音、温度に配慮した睡眠環境をつくりましょう」
寝る前のスマホやPCのブルーライトは、睡眠障害を助長します。おおよそ睡眠の2時間前には、刺激になる光を遮断し、なるべく間接照明のお部屋で過ごすようにしてください。就寝前は、スマホは見ずに、Podcastやラジオ、音楽といった耳からの情報のみにして寝落ちするのがおすすめです。寝る時は部屋は消灯し、室温は24℃~26℃程度に維持します。朝起床時には、必ずカーテンを開け、目の網膜から日光を浴びることが大切です。午前中から日光を取り入れることで、夕方以降に脳内でメラトニンという睡眠に関与するホルモン分泌が促され、夜間に睡眠しやすくなります。
3.睡眠原則③ 「朝食をとること、日中に運動をする、寝る前にリラックスすることで目覚めと眠りのメリハリを」
朝食を抜いている人が最近は多いと思います。簡単なものでいいので、腸を活動させて体に睡眠リズムをつけるためにも、バナナやヨーグルトなど軽めの朝食をとりましょう。日中に軽めの運動を取り入れることで身体も適度に疲れさせましょう。脳疲労だけでは、夜間の睡眠は難しいです。就寝前2~3時間から、リラックスモードになるために、入浴(バスタブにつかる)やヨガなど呼吸法など取り入れることも良いです。ただし、寝床に入るのは、眠くなってから!眠くないのに、ベッドに入っても、逆に寝落ちできません。眠くなるまでは、ソファなど別の場所で眠くなるまで待ちましょう。
4.睡眠原則④「カフェイン、お酒、たばこなどの嗜好品を控えましょう」
コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクといったカフェイン飲料は午後3時以降は控えてください。睡眠障害につながってしまいます。寝酒もかえって不眠を悪化させることが知られています。寝つきはよくなることがあるかもしれませんが、睡眠が浅くなり中途覚醒が増えますので、寝る前の飲酒は控えてください。寝る直前の夕食や、夜食なども不眠につながりやすいです。食事は睡眠の2~3時間前までに終わらせましょう。喫煙される方は、就寝時間の3時間前からはタバコは控えてください。
5.睡眠原則⑤「眠れない、眠りに不安を感じたら、すぐに専門家に相談を」
睡眠不足は肥満・メタボリックシンドローム、循環器系疾患(高血圧、心筋梗塞、狭心症、脳卒中)、うつ病などの発症リスクとなるとともに、仕事の効率も低下させます。このため、慢性的な睡眠不足にならないよう工夫する必要があります。
交替制勤務は、体内時計の不調を招きやすく、適切な睡眠時間の確保を困難にし、健康リスクを高めます。このため、仮眠のとり方や光の浴び方を工夫し、リスクを最小限にとどめる方法を身につけましょう。
睡眠環境、生活習慣、嗜好品のとり方を改善しても、睡眠休養感が高まらない場合、不眠症、閉塞性睡眠時無呼吸等の睡眠障害、うつ病などの睡眠障害が隠れている可能性がありますので、医師にご相談ください。